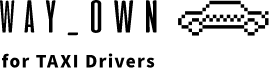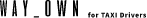大分県とはどのような場所でしょうか。
こちらの記事では、大分県の特徴や食文化について紹介していきます。
大分県の特徴
大分県は九州の北東部に位置しており、福岡県、熊本県、宮崎県と隣接しています。県土の約7割が森林や野原となっており、「九州の屋根」と呼ばれる、くじゅう連山をはじめ鶴見岳や由布岳などの山々が連なっています。
県南部の沿岸部は雨の多い地区であり、1年を通じて高温多湿な気候となっています。佐賀関半島から中津市にいたる海岸一帯は気温が平均15~16℃と温暖であるのが特徴です。一方、湯布院や久住山などの避暑地を擁する西部山岳部の冬は、冷えこみが厳しく気温が-3℃近くまで下がることもあります。
大分県は、別府温泉、由布院温泉をはじめとする温泉地としても有名です。県内のいたるところで温泉が湧出しており、源泉数と湧出量はともに日本一を誇る「おんせん県」です。
大分県の食文化
今回は北部地域、中部地域、西部地域、南部地域に分けて、それぞれの食文化を紹介します。
<北部地域> 郷土に残る多彩な行事食
北部地域は、中津城下町の風情が残る中津市や神仏習合文化の原点となる山岳宗教「六郷満山」が開かれた国東市(くにさきし)、唐揚げ専門店の発祥地として知られる宇佐市など個性豊かな地域で構成されています。
大分県の北西端に位置する中津市と隣接する宇佐市では、古来より「物相(もっそう)ずし」が食べられてきました。「物相」とは、ごはんの量を測る器やごはんを一人前ずつ盛って出す器のことです。4月の金毘羅祭り(こんぴらまつり)や2月の稲荷祭りのあとに食べられる行事食で、具材を混ぜこんだ酢飯を物相に入れて、上から押しぶたで上から圧力をかけてつくられていました。皆が平等に食べられるように、定量で切り分けるために物相を使ったといわれており、米が貴重な時代にはうってつけの食べ方でした。
県内唯一の村である姫島村は、好漁場になっており、水産業が盛んです。村に伝わる「鯛麺」は、茹でたうどんの上に酒や塩、醤油とともに煮こんだ尾頭つきのタイを一匹丸ごとのせた、シンプルでありながら豪華な郷土料理です。
「鯛麺」と「対面」が同じ発音であることから、婚礼をひかえた両家の顔合わせの会や婚姻席の際に縁起物として提供されました。ひと昔前は、家庭でつくったお手製のうどんを使うのが一般的だったため、とてもコシが強かったそうです。
<中部地域> 西洋文化の影響を受けた食文化
中部地域は、由布市、別府市、大分市、臼杵市(うすきし)などの市町村で構成されています。多彩な観光スポット、海の幸・山の幸、アート、スポーツなど魅力あふれる地域であり、多くの観光客が訪れています。
地域に面した別府湾では、船びき網漁業や小型底びき網漁業など様々な漁業が営まれており、約300種類の魚種が生息しています。とくに船びき網で獲れるシラスは「豊後別府湾ちりめん」として有名です。また、日出町(ひじまち)にある日出城址の下に広がる海には、海底から真水が湧き出している海域があります。そこで獲れるマコガレイが非常に美味だったことから「城下かれい」と呼ばれるようになり、ブランディングされています。
戦国時代、キリシタン大名の大友宗麟(おおとも そうりん)は大分市を統治し、最盛期には九州の大半を支配下に治めました。1551年にポルトガル船が入航してからは西洋文化が流入し、この時期に輸入され大友宗麟に献上されたかぼちゃは、「宗麟かぼちゃ」と名付けられ、現在でも栽培が続けられています。
江戸時代末期になると、国府は府内藩、日出藩、臼杵藩などに分立しました。かつて大友宗麟が治めていた臼杵藩では、「黄飯」が食べられており、殿様が贅沢な赤飯の代わりにつくらせ、家来にも振る舞ったのがのはじまりといわれています。乾燥したくちなしの実で黄色く染まったこの料理は、一説によるとキリシタン大名だった大友宗麟が南蛮貿易をおこなっていたことから、スペインから渡来したパエリアを模したのではないかともいわれています。
<西部地域> 無駄なく食べる工夫がされた魚料理
西部地域は、熊本県と福岡県に接しており、竹田市、日田市、九重町、玖珠町から構成されています。
日田地域では「たらおさ」がお盆に欠かせない料理となっています。たらのエラと内臓を干したもので、巨大な歯ブラシのような独特な形状が特徴です。「たらおさ」は独特の臭いがするので途中で水を何回か取り替えながら柔らかく戻し、適当な大きさに切ったものを甘辛く煮こんで食べるのが一般的です。大分県では、アジやタイなどさまざまな魚種が水揚げされますが、たらは獲れないため、「たらおさ」は北海道の稚内市から運びこまれます。
交通インフラの整備されていない江戸時代、海の遠い竹田市では、海魚は貴重な食材として珍重されており、新鮮な魚介を食べる機会も稀でした。そこから、希少な魚介を無駄なく食べるために生み出された料理が「頭料理」です。
「頭料理」は、アラやクエやハタといった大型魚が用いられ、身はもちろん、エラや胸ビレ、内臓など普段なら捨ててしまう部位も湯引きして食べます。傷みやすい魚も一度調理してしまえば日持ちするため、年の暮れや正月の来客などの際に振る舞われました。現在では、一般家庭で「頭料理」が食卓に並ぶことは少なくなりましたが、ひと昔前は、年の暮れになると広い縁側などで大型魚を捌く家庭も珍しくありませんでした。
<南部地域> 人々の暮らしから生まれた素朴な料理
南部地域は、佐伯市(さいきし)と豊後大野市から構成されています。九州一大きな面積を持つ市である佐伯市は、海の幸・山の幸に恵まれており、海と山の地域資源を活用した新たな観光事業の推進など活発に取り組んでいます。
佐伯地域の漁師町に伝わる調味料に「ごまだし」があります。年間を通じて水揚げされる「エソ」が使われることが多く、焼いたエソをほぐしたものに、醤油、ごま、みりんを加えてつくられます。ごまが高い抗酸化作用があるため、保存がきき、つくり置きできるので、様々な料理に使われます。
また、豊後大野地域の農村の暮らしから生まれた郷土菓子として「じり焼き」があります。小麦粉を水でゆるく溶いた生地をクレープのように薄く焼いて、黒砂糖やカボチャのあんを巻いて食べます。昔は子どものおやつとしてはもちろん、農作業の間食などに食べられていましたが、現在は学校給食の献立に盛り込まれていたり、地元のスーパーなどで販売されていたりします。名前の由来は、「じりじりと生地を焼いたから」や「水の多い状態を『じりい』(大分の方言で、「ゆるんでいる」という意味)ということから」など諸説あります。